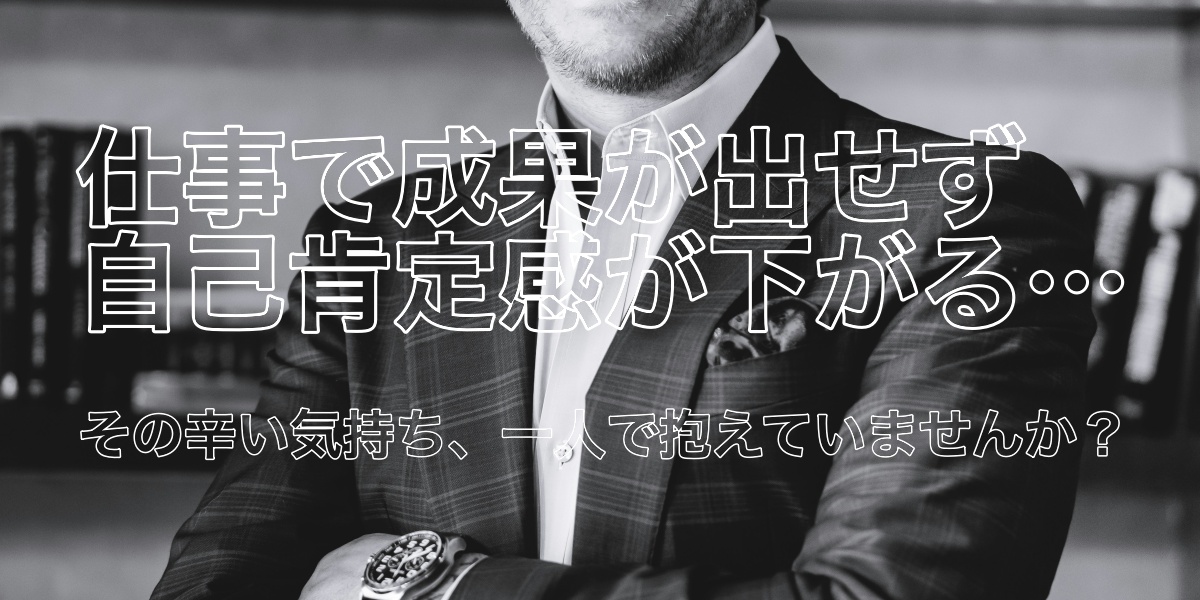仕事で成果が出せず自己肯定感が下がる…その辛い気持ち、一人で抱えていませんか?
「毎日がんばっているのに、思うように成果が出ない…」「周りの同僚は活躍しているのに、自分だけが取り残されている気がする…」
20代、30代のビジネスパーソンにとって、仕事の成果は自身の評価やキャリアに直結する大きな関心事です。しかし、誰もが常に右肩上がりの結果を出し続けられるわけではありません。仕事で成果が出ない時期が続くと、焦りや不安が募り、次第に「自分はダメな人間なんだ」と自己肯定感が下がってしまうのは、決して珍しいことではないのです。
その辛い気持ち、誰にも相談できずに一人で抱え込んでいませんか?
この記事であなたが得られること
この記事では、仕事で成果が出ずに自己肯定感が下がってしまったあなたが、その苦しい状況から抜け出し、再び自信を取り戻すための具体的な方法を、順を追って解説します。
- なぜ自己肯定感が下がってしまうのか、その根本原因がわかります。
- ついやってしまいがちなNG行動を理解し、負のスパイラルを断ち切れます。
- 明日から実践できる、自己肯定感を高めるための具体的なアクションがわかります。
- それでも状況が改善しない場合の、次の選択肢を知ることができます。
この記事を読み終える頃には、あなたの心は少し軽くなり、「自分にもできるかもしれない」と前向きな一歩を踏み出す勇気が湧いてくるはずです。
なぜ?仕事で成果が出ないと自己肯定感が下がってしまう5つの原因
そもそも、なぜ仕事で成果が出ないと、これほどまでに自己肯定感が下がってしまうのでしょうか。その背景には、いくつかの心理的な要因が複雑に絡み合っています。
原因1:他人と比較してしまい、劣等感を抱くから
SNSや社内チャットで、同僚や友人の活躍が簡単に目に入る現代。「同期が大きなプロジェクトを任された」「後輩が先に昇進した」といった情報に触れるたびに、無意識に自分と比べてしまい、「それに比べて自分は…」と劣等感を抱きがちです。他者との比較からくる自己嫌悪は、自信をさらに失わせ、仕事への意欲をも削いでしまう大きな原因の一つです。
原因2:「成果=自分の価値」と無意識に結びつけてしまうから
仕事で高い成果を出すことは素晴らしいことですが、いつの間にか「仕事の成果」と「自分自身の人間的な価値」をイコールで結びつけてしまうことがあります。この考え方に陥ると、成果が出ているときは自信に満ち溢れますが、一度成果が出なくなると、まるで自分の存在価値そのものを否定されたかのように感じてしまい、自己肯定感が大きく揺らいでしまうのです。
原因3:完璧主義で、自分のハードルを上げすぎているから
「常に120%の結果を出さなければならない」「絶対に失敗は許されない」といった完璧主義の傾向がある人は、自分で設定した高すぎるハードルに苦しめられることがあります。どんなに努力しても、常に完璧な成果を出すことは困難です。そのため、少しでもうまくいかないことがあると、「自分は期待に応えられなかった」と過度に自分を責め、自己肯定感を下げてしまうのです。
原因4:失敗を過度に恐れ、ネガティブ思考に陥るから
過去の失敗体験がトラウマとなり、「また失敗するかもしれない」という恐怖心から、新しい挑戦に踏み出せなくなることがあります。失敗を恐れるあまり、物事を悲観的に捉える癖がつき、行動する前から「どうせうまくいかない」とネガティブな思考に支配されてしまいます。この思考パターンが、成長の機会を逃し、自己肯定感を低くする悪循環を生み出します。
原因5:努力の方向性が間違っていて、報われないと感じるから
自分では一生懸命努力しているつもりでも、その方向性が会社の評価基準やプロジェクトの目的とずれている場合、なかなか成果に結びつきません。「こんなに頑張っているのに、なぜ評価されないんだ」という思いは、「自分の努力は無駄だ」という無力感につながり、仕事へのモチベーションと共に自己肯定感を低下させてしまうのです。
【要注意】自己肯定感が低い時にやりがちなNG行動3選
自己肯定感が下がっているときは、視野が狭くなり、無意識のうちに状況をさらに悪化させる行動をとってしまいがちです。もし当てはまるものがあれば、少し立ち止まって考えてみましょう。
NG行動1:自分を責め続け、さらに追い込んでしまう
「なぜ自分はできないんだ」「自分の能力が低いからだ」と、成果が出ない原因をすべて自分のせいにして責め続けてしまうことです。しかし、自分を責めても問題は解決しません。むしろ精神的に自分を追い込み、思考停止に陥ることで、さらに自己肯定感を低下させるという負のスパイラルに陥ってしまいます。
NG行動2:「どうせ無理だ」と新しい挑戦を諦めてしまう
一度の失敗や成果が出ない状況が続くと、「自分には才能がない」「何をやっても無駄だ」と感じ、新しい仕事や役割への挑戦を避けるようになります。失敗を恐れて行動しなくなると、成功体験を積む機会も失われ、自信を回復することがますます難しくなってしまいます。
NG行動3:同僚や上司への相談を避け、一人で抱え込む
「こんなことで相談したら、能力がないと思われるのではないか」「呆れられるかもしれない」といった不安から、誰にも相談できずに一人で問題を抱え込んでしまうケースです。しかし、一人で悩んでいても解決策が見つからず、孤独感やストレスが募るばかりか、最悪の場合、メンタルヘルスに不調をきたす可能性もあります。
成果が出ない辛い状況から抜け出す!自己肯定感を高める7つのステップ
では、どうすればこの辛い状況から抜け出し、自己肯定感を取り戻すことができるのでしょうか。ここでは、明日から実践できる7つの具体的なステップをご紹介します。
ステップ1:まずは「できていること」に目を向ける
成果が出ないときは、つい「できていないこと」ばかりに意識が向きがちです。しかし、どんな状況でも、あなたができていることは必ずあるはずです。
小さな成功体験を記録する習慣をつける
どんなに些細なことでも構いません。手帳やスマートフォンのメモアプリに、その日できたことを3つ書き出す「スリーグッドシングス」などを実践してみましょう。
- 今日のタスクを時間内に終えられた
- 苦手なAさんへの電話を乗り切った
- 朝、予定通りに起きられた
この「小さな成功体験」の可視化と積み重ねが、失った自信を少しずつ取り戻すきっかけになります。
自分の強みや得意なことを客観的に把握する
自分では当たり前だと思っていることでも、他人から見れば立派な強みである場合があります。過去に褒められたことや、苦労せずにできたことを思い出し、自分の強みや得意なことをリストアップしてみましょう。信頼できる友人や家族に「私の良いところって何だと思う?」と聞いてみるのも有効です。
ステップ2:思考の癖を変えるトレーニング
自己肯定感の低さは、物事の捉え方、つまり思考の癖に大きく影響されます。意識的に思考のトレーニングを行うことで、ネガティブな感情をコントロールしやすくなります。
ネガティブな言葉をポジティブな言葉に言い換える(リフレーミング)
リフレーミングとは、物事を見る視点(フレーム)を変えて、ポジティブに捉え直す思考法です。出来事の解釈を変えるだけで、気持ちが前向きになるのを実感できるはずです。
|
ネガティブな捉え方 |
ポジティブな捉え方(リフレーミング例) |
|
仕事でミスをしてしまった… |
このミスのおかげで、改善点が見つかった!次は成功できる。 |
|
自分は心配性だ… |
慎重に物事を進められる、リスク管理能力が高い。 |
|
上司に注意された… |
成長するための具体的なアドバイスをもらえた。期待の表れだ。 |
|
計画性がない… |
状況に応じて柔軟に対応できる、アドリブに強い。 |
他人と比較するのをやめ、「過去の自分」と比べる
他人との比較は、劣等感を生む大きな原因です。比較する相手は「他人」ではなく、「過去の自分」に設定しましょう。「1ヶ月前より、この作業が速くなった」「半年前にはできなかった、この仕事ができるようになった」というように、自分自身の成長に目を向けることが大切です。
ステップ3:具体的な仕事の進め方を見直す
思考法だけでなく、実際の仕事の進め方を見直すことも、状況を好転させるために重要です。
目標を細分化し、達成可能な小さなゴールを設定する
大きすぎる目標は、達成までの道のりが遠く、途中で挫折しやすくなります。最終的なゴールはそのままに、そこに至るまでの中間目標を細かく設定しましょう。「今日はこの資料の骨子を作る」「今週中にA社への提案を完了させる」といった小さなゴールを一つひとつクリアしていくことで、達成感が得られ、モチベーションを維持しやすくなります。
上司や同僚にフィードバックを求め、客観的な評価を得る
一人で悩まず、勇気を出して上司や同僚に「この件について、ご意見いただけますか?」「もっと良くするために、どうすればいいと思いますか?」などと相談し、フィードバックを求めてみましょう。自分では気づかなかった課題や改善点が見つかるかもしれません。また、客観的な評価を得ることで、「自分はここができていなかったのか」と冷静に現状を分析でき、次のアクションにつなげることができます。
ステップ4:心と体を整える習慣を身につける
仕事のパフォーマンスは、心と体の健康状態に大きく左右されます。自分自身をケアすることも、自己肯定感を高める上で非常に重要です。
仕事以外の趣味や好きなことを見つけ、気持ちを切り替える
仕事のことばかり考えていると、視野が狭くなりがちです。意識的に仕事から離れて、趣味に没頭したり、友人と会って話したり、好きな音楽を聴いたりする時間を作りましょう。心がリフレッシュされることで、新たな視点やエネルギーが生まれます。
それでも状況が改善しない場合は?
ここまで紹介したステップを試しても、どうしても辛い状況が続く、あるいは今の職場環境に根本的な問題があると感じる場合は、環境を変えることも考える必要があります。
部署異動や転職も一つの有効な選択肢
努力しても成果が出ないのは、あなたの能力不足ではなく、単に今の仕事や職場環境があなたに合っていないだけかもしれません。自分の強みや特性を活かせる部署への異動を願い出たり、思い切って転職活動を始めたりすることも、自分を守り、キャリアを前進させるための有効な選択肢です。
キャリアのプロに相談して、自分の市場価値を客観的に知る
「自分に合う仕事がわからない」「転職する自信がない」という場合は、転職エージェントやキャリアコーチといったキャリアの専門家に相談してみるのがおすすめです。プロの視点からあなたの強みや経験を客観的に評価してもらうことで、自分では気づかなかった可能性や、現在の転職市場における自分の価値(市場価値)を知ることができます。
市場価値を知る方法
- 転職エージェントに登録し、キャリア面談を受ける: 多くの転職支援実績から、客観的な市場価値を教えてくれる。
- 転職サイトの診断ツールを利用する: 年収査定などのツールで、簡易的に市場価値を把握できる。
- 求人情報を調べる: 自分のスキルや経験に近い求人の給与水準や求められる要件を確認する。
仕事で成果が出せず自己肯定感が下がる…その辛い気持ち、一人で抱えていませんか?まとめ
仕事で成果が出せずに自己肯定感が下がるのは、あなたが真剣に仕事に向き合っている証拠でもあります。決して自分を責めすぎないでください。
大切なのは、他人と比較して落ち込むのではなく、過去の自分と比べて少しでも成長できている点を見つけることです。そして、今日ご紹介した方法の中から、自分にできそうなことを一つでもいいので試してみてください。
小さな成功体験を積み重ね、自分を認めてあげることで、自己肯定感は少しずつ回復していきます。焦らず、あなたのペースで、着実に一歩ずつ前に進んでいきましょう。